こんにちは、あべです。
2023年5月5日に、X(旧Twitter)で次のポストをしました。
※うまく表示されない場合があります。その場合は、以下の「ポスト全文」でご確認ください。
このポストでは、秋田県の少子化と高齢化の現状、そしてそれに伴う課題について考えました。
この日は、「子どもの日にも関わらず、子どもの数が減少し続ける現実に直面し、地域社会としてどのように対応すべきかを考える必要がある」と感じました。
ポスト全文
今日は子どもの日ですね!
そんな今日の地元新聞一面の見出しは、『子どもの数 42年連続減』とありました。また、秋田県の子どもの割合は12年連続全国最低だそうです。高齢化率は全国1位。これは大変です!
『なんとへばいべが?(←どうすれば良いのか?)』そんな事を考えながら子育て奮闘中です。
セルフ解説
なぜこのポストを書いたのか
私は現在、秋田県で3人の子どもを育てながら、介護業界で働いています。
2023年5月5日、子どもの日という特別な日に、地元新聞の一面で「子どもの数 42年連続減」という見出しを目にしました。さらに、高齢化率が全国1位である秋田県の子どもの割合が、12年連続で全国最低であることを知り、地域の未来に対する危機感を抱きました。
子育て中の親として、そして地域社会の一員として、「なんとへばいべが?(どうすれば良いのか?)」と自問し、この現状を共有することで、共に考えるきっかけを作りたいと思い、このポストを投稿しました。
深掘り:このポストで伝えたかったこと
少子化と高齢化の現状
秋田県は長年にわたり少子化と高齢化が進行しています。
2023年時点で、子どもの数が42年連続で減少し、子どもの割合は12年連続で全国最低となっています。さらに、高齢化率は全国で最も高い状況が続いています。これは地域の活力や経済活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
少子化の要因
少子化の要因として、以下の点が挙げられます。
• 経済的負担:子育てや教育にかかる費用が高く、理想の子どもの人数を持てないと感じる家庭が多い。
• 結婚・出産に対する意識の変化:若者の結婚や出産に対する価値観の多様化や、ライフスタイルの変化も少子化の一因。
• 都市部への人口流出:仕事や教育環境の充実を求めて若者が都市部に移住する傾向が強まり、地元に残る人が減少。
高齢化の影響
高齢化が進行すると、今以上に介護や医療の需要が増加し、労働力人口の減少により地域経済の停滞が懸念されます。
特に秋田県のような地方では、若者の流出も相まって、地域コミュニティの維持がより難しくなる可能性があります。
実生活や介護現場との関連性
少子化や高齢化は、単なる統計上の数字ではなく、私たちの生活に直結する大きな課題です。私自身、介護業界で16年間働いてきた中で、日々その影響を肌で感じています。
介護現場での気づき:支える人が減るという現実
介護を必要とする高齢者は年々増え続けています。一方で、少子化の影響を受け、介護職に就く若い世代の数は減少し続けています。
特に、人口減少が進む地域では、「介護が必要な人は増えるが、支える人は減る」 という状況が顕著です。
たとえば、介護施設では人手不足が慢性化し、家庭では老々介護が当たり前になりつつあります。このままでは、高齢者を支える社会の仕組み自体が立ち行かなくなる可能性もあります。
では、この課題に対して私たちはどう向き合うべきなのでしょうか?
日常生活で意識したいこと:「地域で支え合う」という考え方
この問題を解決するには、介護や子育てを「家族だけの問題」と捉えず、「地域全体で支え合う仕組みをつくる」 という視点が重要になります。
例えば、
• 地域の子どもたちと高齢者が自然に交流できる場をつくる
→「子ども食堂」や「世代間交流イベント」などを活用する
• 若い世代が地元に定着しやすい環境を整える
→ 働きながら子育てしやすい地域づくりを進める
• 介護や子育てを「他人ごと」にしない意識を持つ
→ 地域の支援制度を知り、必要な人に情報を届ける
子どもの成長も、高齢者の生活も、決して「個人や家族だけの課題」ではありません。
地域全体で助け合い、支え合う仕組みを考えることが、少子化や高齢化の課題を乗り越える一歩になるのではないでしょうか。
この問題について考える
この記事を読んで、少子化や高齢化について「これは大変な問題だ」と感じた方もいるかもしれません。
一方で、「でも、どうしようもないんじゃないか」と思った方もいるでしょう。
確かに、個人の力で社会全体の流れを変えることは簡単ではありません。ですが、問題意識を持ち、自分なりに考えたり、周囲と話し合ったりすることは、私たち一人ひとりにできることです。
たとえば、以下のような視点で考えてみるのはどうでしょうか?
親の立場なら
子どもがのびのびと成長できる環境をつくるために、地域でできることはないか?
地域の子育て支援の場に関心を持ち、参加してみるのはどうか?
若い世代の立場なら
「結婚や子育ては大変」と言われがちですが、実際にはどんなサポートがあれば安心できるのか?
仕事や生活とのバランスを考えたとき、社会の仕組みとして改善できることは何か?
地域の一員として
子育て中の家庭や高齢者を支えるために、地域ぐるみでできることはあるのか?
例えば、近所の子どもたちや高齢者と自然に関われる場をつくることはできるか?
この問題に「正解」はありません。でも、こうして一人ひとりが「自分ごと」として考えることが、社会を少しずつ変えるきっかけになるのではないでしょうか。
おわりに
この記事では、私自身が過去にX(旧Twitter)でポストした内容を改めて深掘りしました。
当時は伝えきれなかった「価値観」や「ものの見方」を通じて、少しでも新たな気づきやヒントになれば嬉しいです。
この記事のまとめ:
- 特に秋田県では少子化と高齢化が深刻な問題となっている。
- 経済的負担や人口流出が少子化の主な原因。
- 高齢化の進行により介護や地域コミュニティの維持が課題。
- 地域ぐるみでの支援が必要であり、個人でもできることがある。
現在は『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にポストしています。
最新の気づきや学びをリアルタイムで発信中です。ぜひお気軽に遊びに来てください!(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
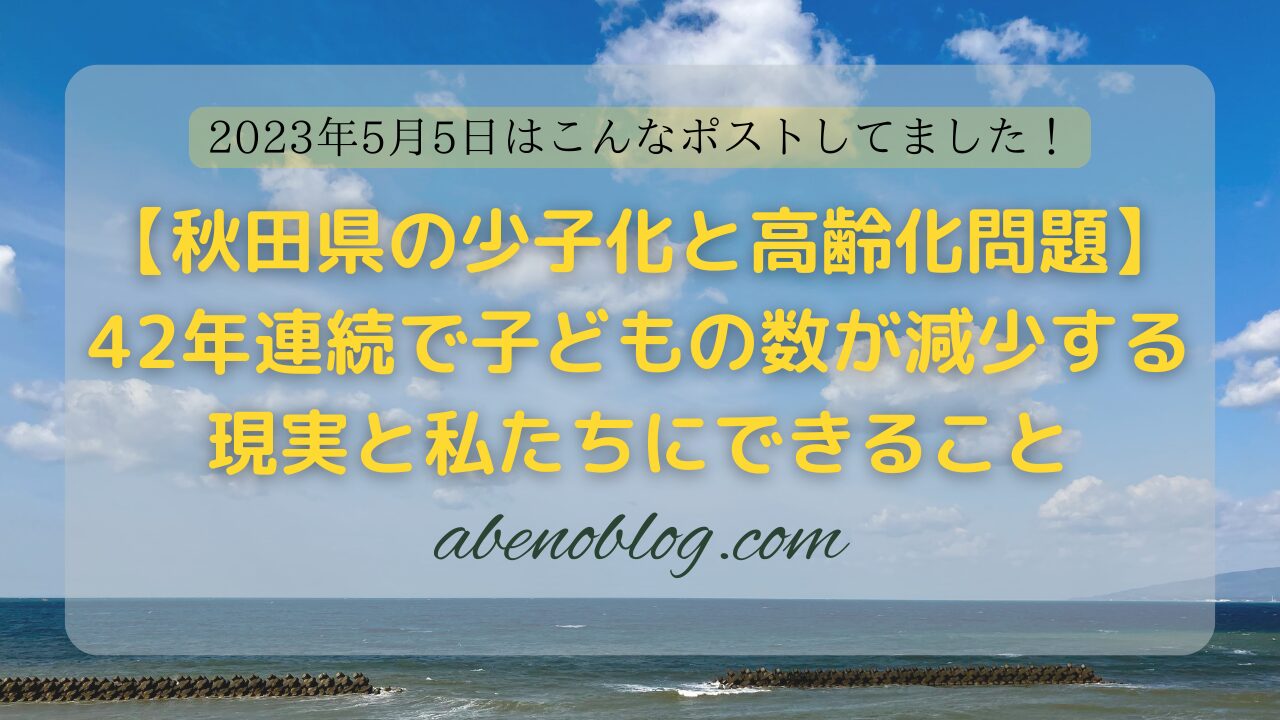
コメント