こんにちは、あべです。
2023年4月28日に、X(旧Twitter)で次のポストをしました。
※うまく表示されない場合があります。その場合は、以下の「ポスト全文」でご確認ください。
このポストでは、「介護予防」と「フレイル予防」について考えました。
「介護が必要になる前に、どんな準備ができるのか?」という視点から、私は特に「ヒアリングフレイル」という概念に注目しています。
ポスト全文
私は【介護予防】に注目しています。
これからは、介護が必要となる前に出来ることがたくさんあると思うんですね。
その1つにフレイル予防があります。
さらにヒアリングフレイル予防という概念があります。
少しでも「対処から予防へ」という思いで、微力ながらブログ記事にしました。
m(_ _)m
セルフ解説
なぜこのポストを書いたのか
私が介護業界に長く携わる中で感じたのは、「もっと早く予防策を知っていれば、介護が必要にならなかったかもしれない」というケースが多いことです。
高齢者の身体機能の低下を防ぐ「フレイル予防」はよく知られていますが、実は聴力の衰え(ヒアリングフレイル)も重要な課題です。
「対処から予防へ」という考えを広めるために、このポストを書きました。
深掘り:このポストで伝えたかったこと
フレイルとは?
フレイル(虚弱)とは、加齢によって筋力や認知機能が低下し、介護が必要になるリスクが高まる状態のこと。早めの対策が重要です。
ヒアリングフレイルとは?
聴力が低下すると、人との会話が減り、認知機能の低下や社会的孤立につながります。これを「ヒアリングフレイル」と呼びます。
「対処から予防へ」の重要性
介護が必要になってからの対応ではなく、「まだ大丈夫」と思えるうちからの予防が鍵になります。
「フレイル」については、次の記事でも簡単に解説しています。
実生活や介護現場との関連性
介護の現場では、
「最近、会話が減った」
「テレビの音量が大きくなった」
といった変化が、高齢者の生活の質(QOL)に大きく影響を与えます。
また、補聴器の活用や、聞こえやすい環境づくりが、フレイル予防につながることも実感しています。
「声をかける機会を増やすこと」が、何よりの対策になります。
「ヒヤリングフレイル」については、次の記事でも簡単に解説しています。
行動のヒント
「この記事から得た学びをどう行動に活かせるか?」
- 身近な高齢者に「最近、聞こえづらいことある?」と声をかけてみる
- 会話の機会を増やし、日常的なコミュニケーションを意識する
- 定期的な聴力チェックを習慣にする(特に65歳以上)
- テレビやラジオの音量が大きくなっていないか気にしてみる
ちょっとした気遣いが、大きな予防策につながります。この変化は、身近な家族であればあるほど、気づきにくいものです。ですので、家族以外の関わりがとても重要です。ぜひ社会参加の機会や接点は持ち続けてほしいと思います。
おわりに
この記事では、私自身がX(旧Twitter)でポストした内容を深掘りし、介護予防における「フレイル」と「ヒアリングフレイル」の重要性について考えました。
特に「聴力の低下」が高齢者の生活に及ぼす影響は大きく、「聞こえ」に関する気づきが介護予防の第一歩になると感じています。
この記事のまとめ
- フレイル(虚弱)は予防が大切
- ヒアリングフレイルとは、聴力低下による社会的孤立のこと
- 聴力の衰えに気づき、声をかけることが予防の第一歩
現在、私は『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にXで発信しています。リアルタイムの気づきをシェアしているので、ぜひ遊びに来てください!(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
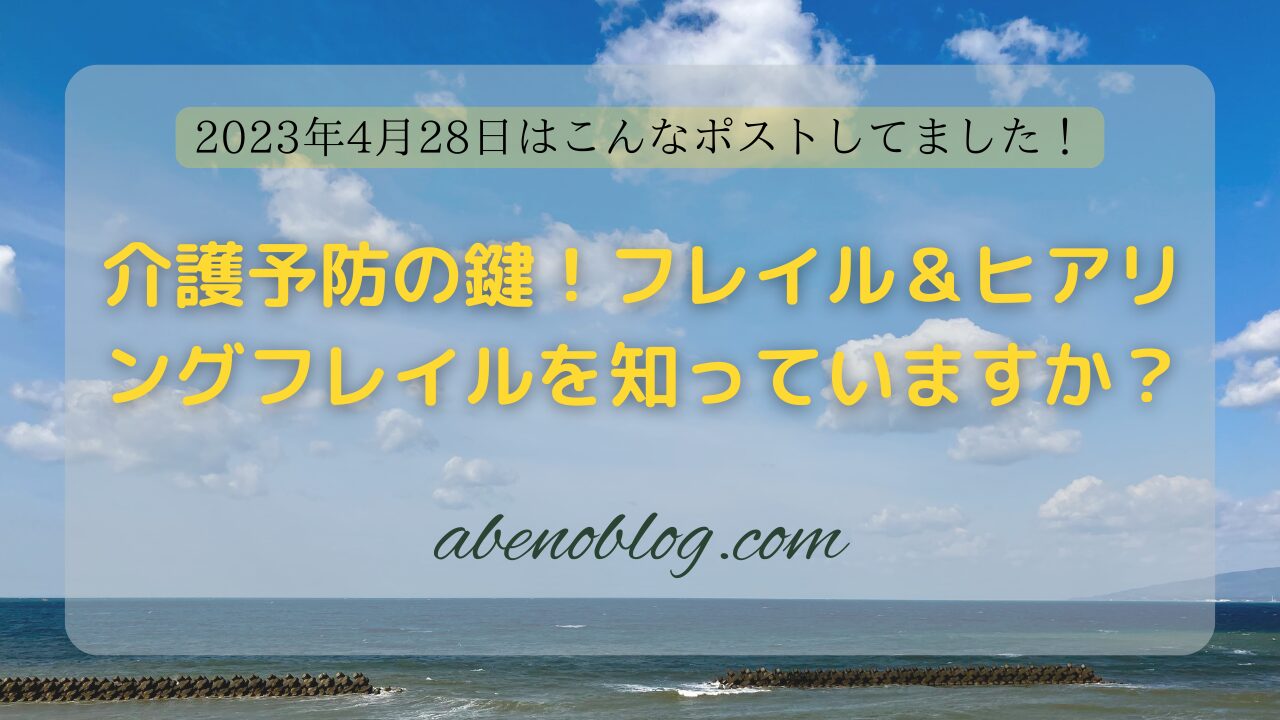

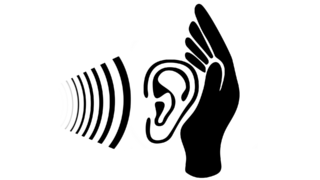
コメント