こんにちは、あべです。
私は15年以上の介護業界の経験をもとに、毎日の実践や気づきをシェアしています。
2023年10月3日は、X(旧Twitter)で次のポストをしました。
このポストでは、「ハインリッヒの法則」という考え方について触れました。
この法則は安全管理の基本として知られていますが、意外と多くの人が「名前だけは知っている」という状況にあります。
そこでこの日の私は、まずは一人でも多くの人に“知ってほしい”と思ったこと。そして、見落とされた異常はないか“意識してみてほしい”という思いでポストを作成しました。
ポスト全文
ナゼの数だけ未然に防げる。事故が起きた時よく出てくる用語に『ハインリッヒの法則』があります。これは、1件の重大な事故の下に29件の軽微な事故があり、その背景に300件の異常があるというもの。実はこの法則、意外と実践は難しいようです。知ってると使うは別モノ。今すぐ問いかけてみて下さい。
セルフ解説
なぜこのポストを書いたのか
この日は、単純に「ハインリッヒの法則」という言葉を、もっと多くの人に知ってもらいたいと思ったからです。
私自身、この法則を知ったのは介護職に就いて数年が経った頃でした。当時、施設内では転倒や文字通りヒヤッとすることが相次ぎ、「なぜこうも続くのか」と悩んでいた時に出会ったのがこの考え方です。
「1件の重大事故の裏には、29件の軽微な事故、さらに300件の異常がある」
この数字を見た瞬間、衝撃を受けました。
私たちが“たまたま防げた”と思っていることの中に、実は多くの「サイン」が潜んでいるという現実に気づきました。それ以来、私は「日々の小さな“ナゼ”を積み重ねることこそが安全管理だ」と意識するようになりました。
そしてこの法則は、介護現場に限らず、どんな職場や家庭にも当てはまる“普遍的な原理”だと思っています。だからこそ、日常的に誰もがこの視点や考え方で物事を捉えられたら良いなと思いました。
ハインリッヒの法則が伝えている本当の意味
ハインリッヒの法則は1930年代にアメリカの労働災害研究者ハーバート・ハインリッヒが提唱したものです。改めて数字で表すと次のようになります。
- 1件の重大事故
- 29件の軽微な事故
- 300件の異常(ヒヤリ・ハット)
この「1:29:300」という比率は、多くの現場で語り継がれてきました。
ですが、この法則の本質は「数字」ではありません。
重要なのは、重大な事故の根底には、必ず小さな見落としが積み重なっているという“気づき”です。
私たちは、目の前のトラブルや事故が起きてから原因を探します。ですが本当に必要なのは、事故が起きる前に“異常”に気づく力です。
例えば、
- 床に置かれたままのカゴ
- 通路のコード
- 誰も注意を向けない小さな段差
こうした“何でもない光景”が、実は300件の中の1つです。
つまり、「大事故を防ぐ力」は、“日常の小さな違和感を拾えるかどうか”にかかっています。
そしてそれを拾う方法こそが、ポストに込めた「ナゼを問う」ことです。
実生活や介護現場との関連性
「ナゼ」が生む安全習慣
介護現場では、「ヒヤリ・ハット報告書」や「リスクマネジメント委員会」などが設けられています。
例えば報告書。この提出を“仕事の一部”としてしか捉えられないと、本来の目的が失われてしまいます。
報告の本質は、「失敗を共有して次に活かすこと」。
ですが、忙しい現場では「また報告か…」「ミスを責められる…」と感じることもあります。
そんな時こそ大切なのが、「ナゼ」という言葉です。
「なぜ起きたのか?」ではなく、
「なぜ気づけなかったのか?」
「なぜこの状況が続いていたのか?」
と原因の背景を探る問いを立てる。
これを繰り返すことで、“人を責める”から“仕組みを見直す”へと視点が変わっていきます。
私はこの考え方を大事にしたいと思っています。
視点や目的が明確であれば、億劫に感じる報告書の作成や、業務上で必要な事務的な記録物も、重大事故を未然に防ぐための重要な予防ツールとして役立てることができると考えます。
家庭でも使えるこの法則
また、この考え方は家庭にも応用できます。
例えば、子どもがコップを倒したとき。
「どうしてこぼしたの!」と叱るのではなく、
「どうしてそうなったと思う?」と一緒に考える。
すると、
- 机の上が狭かった
- 手元を見ていなかった
- 遊びながら飲んでいた
など、行動の背景に目を向けられるようになります。
これはまさに、ハインリッヒの法則の考え方そのものです。
小さな“異常”を共有することで、同じ失敗を繰り返さない。家庭も職場も、「ナゼ」を通して安全で穏やかな空気をつくることができます。
今日から新たな一歩を
この記事をここまで読んでくださったあなたは、きっと何かしら共感や気づきを得てくださったと思います。大切なのは、その気づきを「行動」に変えていくことです。行動が変われば、日常の景色も少しずつ変わっていきます。
ここでは、今すぐ実践できるヒントをご紹介します。
例えば、
・毎日1つ「ナゼ」を書き留める
→ たとえ小さな気づきでも、継続すれば“異常”に敏感な自分が育ちます。
・報告書の目的を「防止」に言い換える
→ “書かされるもの”から、“次を守るためのもの”へ意識が変わります。
・ヒヤリ報告への最初の言葉を「ありがとう」にする
→ 責める習慣から、気づきを称える習慣へと変化します。
どの方法を選ぶか、どのように活かすかはあなた次第です。無理のない範囲で「今の自分にできること」から取り入れてみてください。その行動が、より豊かな日常生活へ向かう、改善に必要な大切な“第一歩”になります。
おわりに
この記事では、私自身が過去にX(旧Twitter)でポストした内容を改めて深掘りしました。当時は伝えきれなかった「価値観」や「ものの見方」を通じて、少しでも新たな気づきやヒントになれば嬉しいです。
この記事のまとめ
- 「ハインリッヒの法則」は“事故の下にある気づき”を可視化する考え方。
- 重大事故は、日常の小さな異常を見逃した結果として起きる。
- “ナゼ”を繰り返すことで、原因を責めずに構造を理解できる。
- 介護現場だけでなく、家庭や職場にも応用可能。
- まずは「小さな違和感」に気づく力を育てることから始めよう。
現在は『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にポストしています。最新の気づきや学びをリアルタイムで発信中です。ぜひお気軽に遊びに来てください!(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
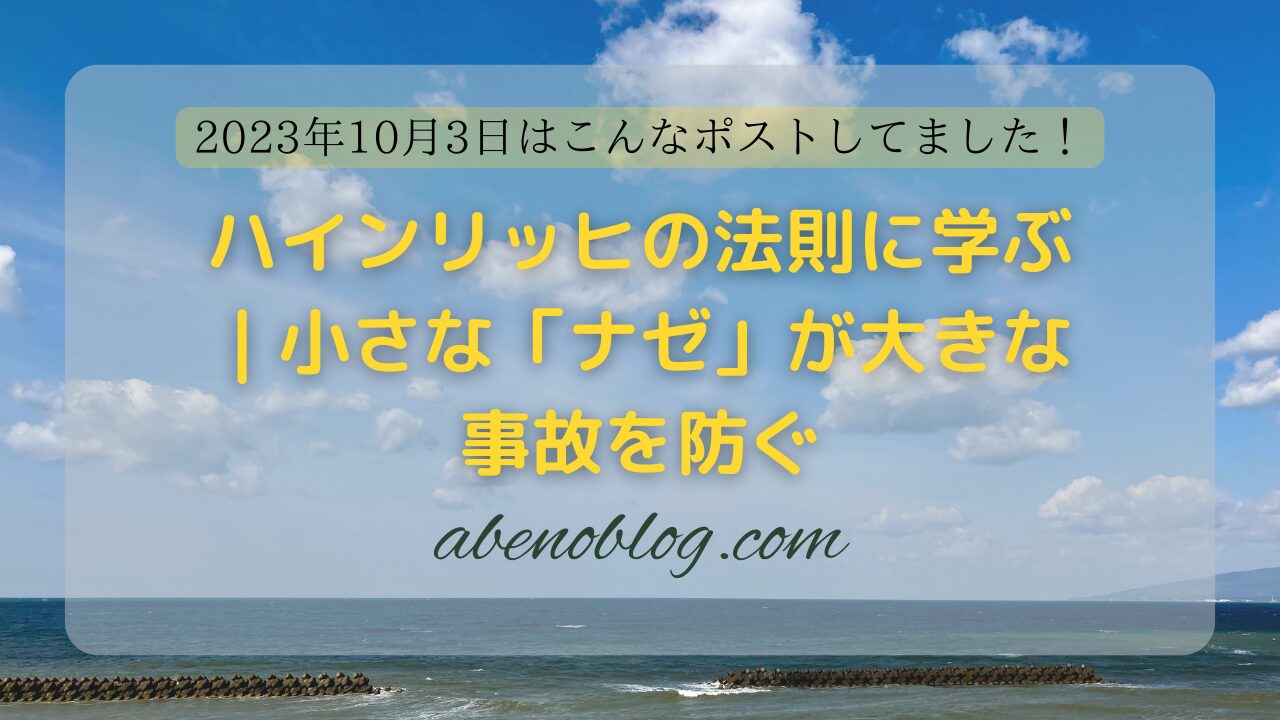
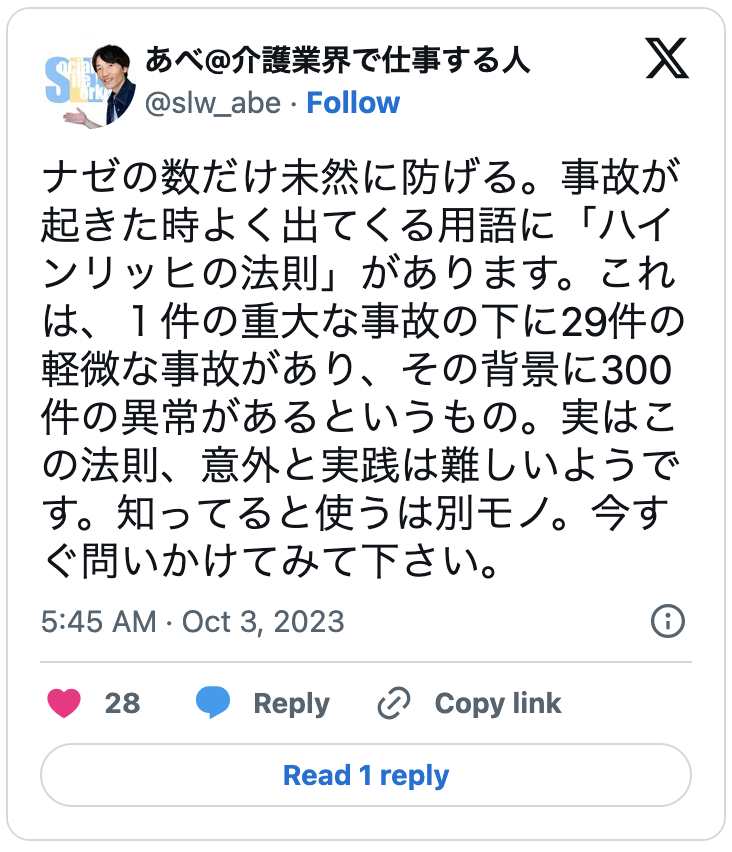
コメント