こんにちは、あべです。
私は15年以上の介護業界の経験をもとに、毎日の実践や気づきをシェアしています。
2023年9月5日、私はX(旧Twitter)で次のポストをしました。
このポストでは、訪問介護サービスを提供する事業所の減少と、それを引き起こす人手不足について考えました。サービスのニーズが増える一方、供給が追いつかない現実に、深く考えさせられました。
ポスト全文
大変です!【訪問介護サービス】を提供している事業所が減っています。3日の地元新聞の1面記事には「休廃止220カ所 社協運営、5年間で13%減」と書かれ「共同通信の全国調査で分かった」とありました。大きな理由は“人手不足“とのこと。サービスは減ってもニーズは増える。とても考えさせられました。
セルフ解説
なぜこのポストを書いたのか
私は20代の頃、訪問介護の管理者をしていました。まだ経験も浅く、日々が挑戦の連続でしたが、従業員はすべて正職員で構成し、責任感のある体制で運営していました。パートタイムの時間休ヘルパーが中心の事業所も多い中、正職員だけで現場を回していたことは、私たちの強みであり挑戦でもありました。
現場では、ヘルパーのニーズがどうしても偏り、特定の利用者や家庭への依頼が集中することがありました。また、訪問介護ならではの「一対一」のケアだからこそ、現場ごとに特有の問題が発生しました。対応の難しさに悩むこともありましたが、それ以上に利用者さんからの「ありがとう」の言葉やご家族の安心した表情に、やりがいを強く感じていました。
ですが、経営的な事情により、私が関わった事業所は廃業を余儀なくされました。当時の私は、介護の現場に必要な支援が地域から一つ消えてしまう現実に直面し、大きな悔しさと無力感を抱いたことを鮮明に覚えています。だからこそ、このニュースを見たときに、ただの数字ではなく、自分の経験と重なり、強い感情が湧き上がりました。
訪問介護事業所が減少する背景
全国的に見ると、訪問介護の事業所数は一見すると増えているように見えます。厚生労働省の調査では、2023年時点で36,905事業所と前年比でわずかに増加しています。ですが、その内情は楽観できるものではありません。
事業所数は増えていても、働く職員は年々減少しています。訪問系サービスに従事する介護職員数は53.8万人と、前年から1.6%減少しました。つまり、箱はあっても中で働く人が足りないため、サービス提供が追いつかないとの見方もできます。
さらに、休止や廃止は全国で相次いでいます。2024年6月から8月のわずか3か月間だけでも、166件が休止、397件が廃止という状況でした。倒産件数も増えており、2024年は過去最多を更新、2025年上半期だけでも45件が確認されています。このペースだと年間100件を超える可能性もあります。
背景には、深刻な人手不足と報酬改定の影響があります。2024年度の介護報酬改定では訪問介護の基本報酬が引き下げられ、経営体力の弱い事業所ほど運営が困難になりました。全国で介護職員は毎年5万人規模で不足すると見込まれており、都市部では有効求人倍率が4倍を超える地域もあるほどです。
つまり、需要が伸びる一方で、現場は支え手を失い続けているというのが現状です。
現場特有の問題と実感
私自身が管理者を務めていたときも、現場には独特の課題がありました。例えば、利用者方の希望するヘルパーが偏ってしまい、特定の職員に負担が集中してしまうことがあります。誰もが行けるわけではなく、相性やご家族との関係性もあるため、シフト調整は常に難題でした。
また、正職員だけの体制は責任感が強い反面、急な欠勤や体調不良のときにカバーできる余力が少なく、組織的に脆弱な一面もありました。それでも、現場で働く仲間は皆真剣で、支え合いながらやり遂げていたことが、今も思い出として残っています。
経営的な事情で廃業に至ったとき、私は「制度や報酬のわずかな変化が、現場を直撃する」ことを身をもって学びました。介護の現場は人と人との信頼関係で成り立っていますが、その土台となる経営が安定していなければ続けることはできません。この矛盾をどう解決していくかは、今も大きな課題です。
行動のヒント
この記事が、あなたの共感や気づきとなったなら、今からできる行動を考えてみてください。
まず、事業所単位で取り組めるのは「業務の見える化」です。訪問介護は一対一のサービスだからこそ、情報共有が難しい側面があります。ICTの導入やアプリを使ったスケジュール管理を進めることで、職員の負担は大きく軽減されることが見込まれています。
次に大切なのは「職員への感謝の言葉」です。人手不足の時代において、働く人を大切にすることが何よりの定着戦略になります。日常的に「ありがとう」を伝えるだけでも、雰囲気は変わります。
そして「地域との連携」を本気で強めることです。地域包括支援センターや他の事業所とつながることで、単独では対応しきれないケースも支え合えるようになります。孤立せず、地域全体での支援体制を目指すことが今後の大きな鍵です。
どのような手段を取るのか、どのように活かすかはあなた次第です。無理なくできることから、ぜひ試してみてください。
おわりに
この記事では、私が2023年9月にポストした「訪問介護事業所の減少」に関する話題を、2025年9月現在の最新データとともに深掘りしました。
20代で管理者をしていた頃の私の経験と、今も続く人材不足や制度の課題は、確かに地続きにあります。当時から変わらない本質的な問題もあり、未来をどう作るかは私たち次第だと痛感します。
この記事のまとめ
- 訪問介護事業所は数字上は増えているが、職員不足で機能していない現実がある。
- 休廃止・倒産は増加傾向で、今後さらに深刻化する可能性が高い。
- 現場は人材偏在や制度の影響など独自の課題を抱え、持続可能性が問われている。
- 小さな改善や地域連携から、未来への一歩を踏み出すことができる。
現在は『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にポストしています。最新の気づきや学びをリアルタイムで発信中です。ぜひお気軽に遊びに来てください!(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
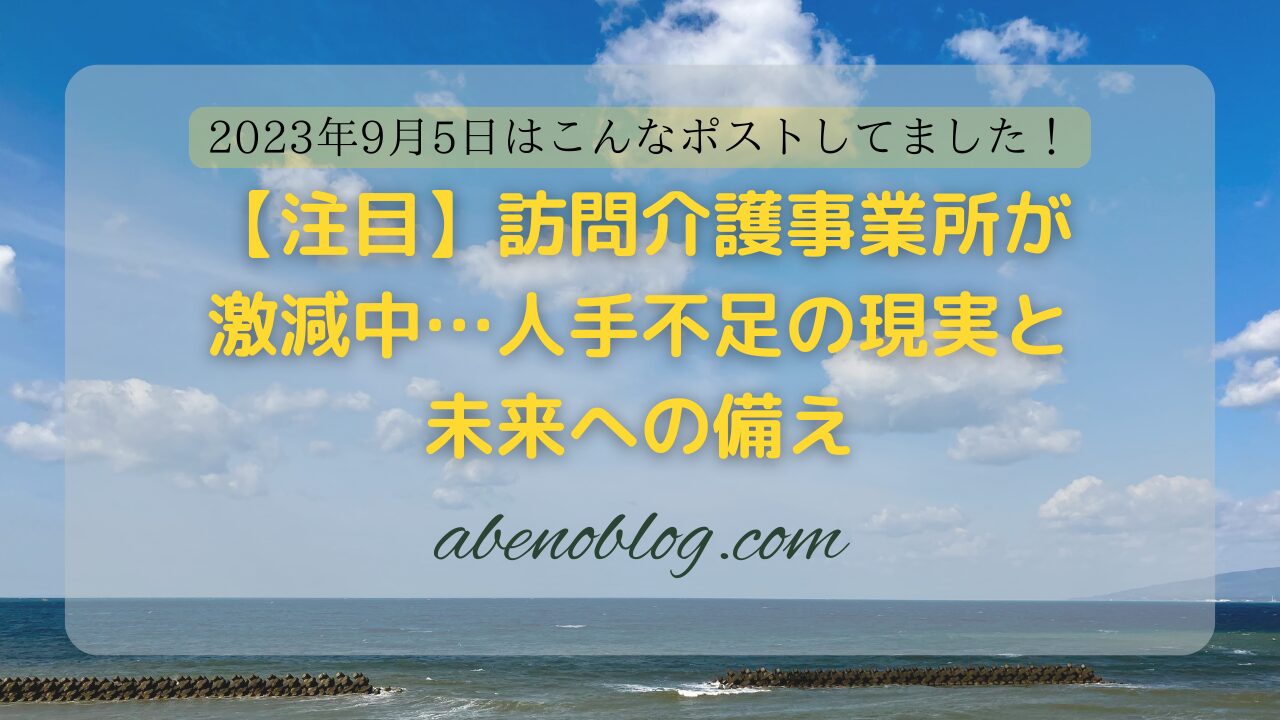
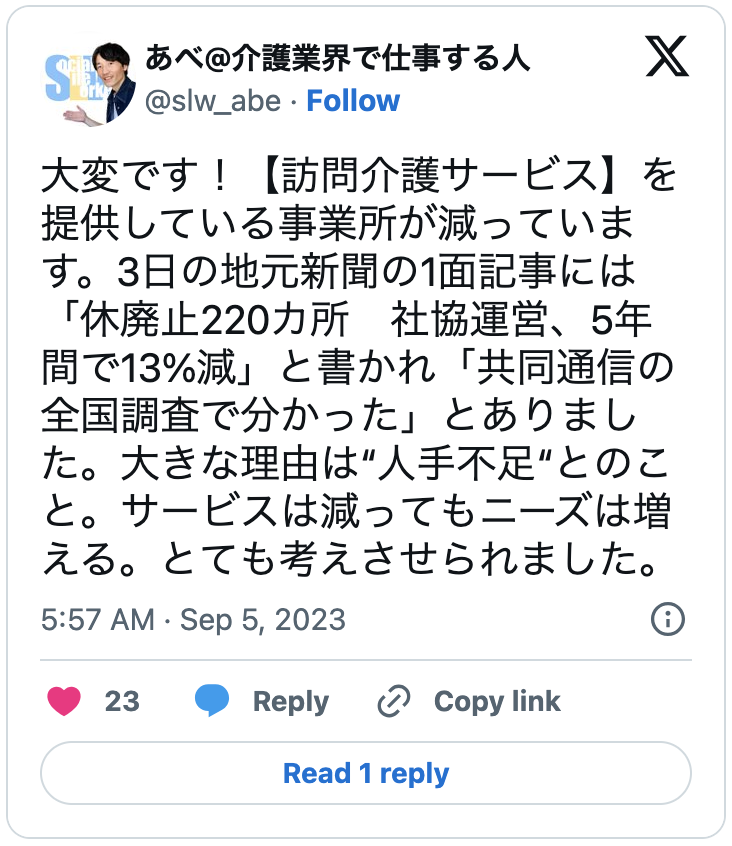
コメント