こんにちは、あべです。
私は15年以上の介護業界の経験をもとに、毎日の実践や気づきをシェアしています。
2023年10月6日はX(旧Twitter)に、次のポストをしました。
このポストでは、「物忘れ」と「認知症」の違い、そして家族がどう受け止め、関わるべきかについて考えました。介護の現場ではよく耳にする言葉ですが、誤解が多く、不安を感じる方も少なくありません。
この記事では、その不安を少しでもやわらげられるよう、専門的な知識と実体験を交えながら解説します。
ポスト全文
「最近ボケてきた。」このセリフ、本人が何か物忘れに気づいた時などに、認知症を心配してよく使われます。私の母も言います。私が直接耳にした場合は、次のように伝えます。「忘れた事に気づけたならまだ大丈夫!もし病気なら忘れた事には気づかない。」コレが物忘れと認知症の大きな違いの1つです。
セルフ解説
なぜこのポストを書いたのか
このポストを書いたきっかけは、実家に帰った際に、母との何気ない会話でした。
ある日、「あれ?あの人の名前、なんだっけ?」と母が言いながら笑っていました。その後すぐに、「最近ボケてきたなぁ」と口にしました。
この“自分で気づいて笑える”という感覚が、実はとても大切だと私は思っています。
介護の現場でも、「物忘れ=認知症」と考える人が多いですが、両者には大きな違いがあります。
そして、その違いを正しく理解しておくことは、本人や家族の安心にもつながります。
私は母の何気ない一言から、「物忘れをどう捉えるか」というテーマを多くの方に知ってもらいたいと思い、このポストを書きました。
物忘れと認知症の違いとは
「忘れたことに気づけるかどうか」が大きな分かれ道
物忘れと認知症の最も大きな違いの一つは、「忘れたことを自覚しているかどうか」です。
例えば、次のようなケースを比べてみましょう。
- 物忘れの場合:「あれ、財布どこに置いたっけ?」と探す。でも後で思い出す、または誰かに言われて思い出す。
- 認知症の場合:財布をなくしたこと自体を忘れている。または「誰かに盗まれた」などと言ってしまう。
この差が、脳の働きの違いを表しています。
物忘れは、誰にでも起こり得る“年齢による変化”であり、脳の記憶処理の一時的な遅れです。
一方で認知症は、脳細胞の変性や萎縮によって「記憶そのものを保持する機能」が損なわれていく病気です。
物忘れ=老化ではない。予防できる余地がある
「年をとれば仕方ない」と思われがちですが、実はそうではありません。脳も身体を鍛えるのと一緒で、“使えば使うほど強く”なります。
また、脳の神経細胞同士は「シナプス」という接合部でつながっています。このつながりは、新しい刺激を受けることで強化されます。
つまり、
- 新しいことに挑戦する
- 人と会話する
- 趣味や日課を楽しむ
といった日常の中の行動が、脳の健康を支えています。
私の母も、不定期に孫と会い世話をすることで、それが良い刺激になっていると感じています。「この前はいつ来たんだっけ?」と一瞬考える時間も、脳がしっかり働いている証拠です。
実生活や介護現場との関連性
家族が「気づき」を支える役割
介護現場では、「最近、母が同じ話を何度もする」という相談をよく受けます。
多くの場合、それは“軽い物忘れ”の段階であり、適切な声かけや環境調整で改善が見られます。
家族ができるサポートとして大切なのは、「責める」ではなく「支える」姿勢です。
例えば、「また同じ話してるよ!」ではなく、「その話、前にも聞いたね。楽しかったよね」と返すだけで、相手の気持ちはまったく違います。
忘れること自体よりも、「忘れたことで責められた」「恥ずかしい思いをした」ことが本人の心を傷つけ、結果的に意欲の低下を招くこともあります。
現場で感じる“早期発見”の大切さ
介護の仕事をしていると、「もっと早く気づけていたら…」と思うケースに何度も出会います。
認知症は“進行性”の病気ですが、早期発見・早期対応によって進行を遅らせることが可能です。
本人や家族が「何かおかしい」と感じた時点で、医療機関に相談することが大切です。
例えば、もの忘れ外来や脳神経内科では、専門医が記憶力のテストや脳画像検査などを行ってくれます。“気づけた時がスタートライン”です。
今日から新たな一歩を
この記事をここまで読んでくださったあなたは、きっと何かしら共感や気づきを得てくださったと思います。大切なのは、その気づきを「行動」に変えていくことです。行動が変われば、日常の景色も少しずつ変わっていきます。
ここでは、今すぐ実践できるヒントをご紹介します。
例えば、
・会話の「ツッコミ」をやめて「共感」に変える
→「またその話?」ではなく、「その話好きなんだね」と返すだけで、安心感が生まれます。
・“脳の散歩”を意識する
→外に出て季節の変化を感じたり、人と軽く会話するだけでも脳は活性化します。
・「忘れてもいい」と思える環境づくり
→メモ帳やカレンダーに予定を書くのは、「忘れないため」ではなく「安心して忘れるため」。その意識の転換が大切です。
どの方法を選ぶか、どのように活かすかはあなた次第です。無理のない範囲で「今の自分にできること」から取り入れてみてください。その行動が、より豊かな日常生活へ向かう、改善に必要な大切な“第一歩”になります。
おわりに
この記事では、私自身が過去にX(旧Twitter)でポストした内容を改めて深掘りしました。当時は伝えきれなかった「価値観」や「ものの見方」を通じて、少しでも新たな気づきやヒントになれば嬉しいです。
この記事のまとめ
- 「忘れたことに気づける」なら、それは病気ではなく自然な物忘れ。
- 認知症は“忘れたことを忘れる”状態。早期発見が何より大切。
- 家族の支え方ひとつで、本人の安心感と意欲は大きく変わる。
- “責める”より“支える”を意識して、笑顔で過ごせる環境を。
現在は『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にポストしています。最新の気づきや学びをリアルタイムで発信中です。ぜひお気軽に遊びに来てください!(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
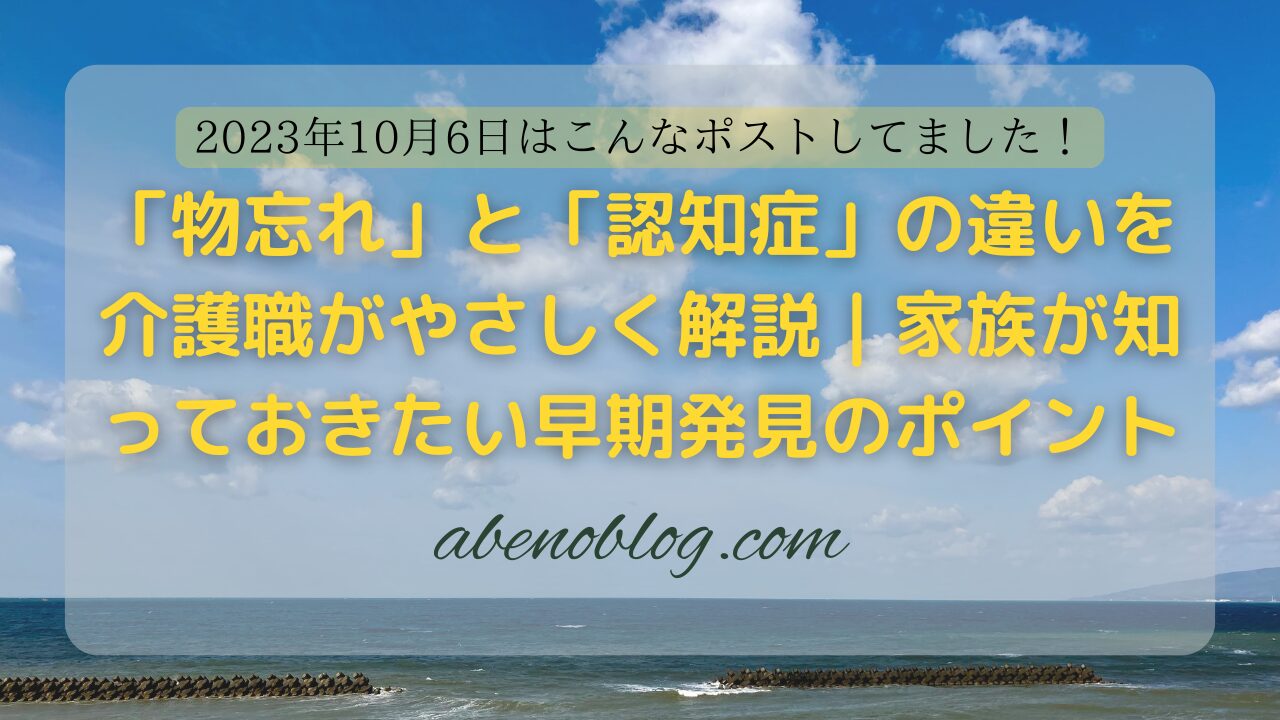
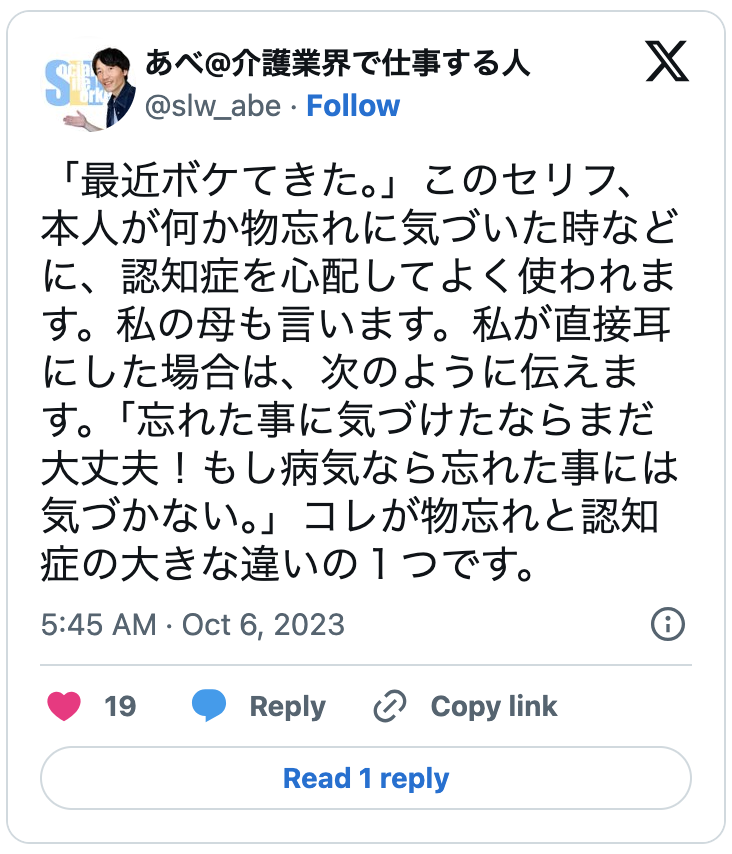
コメント