こんにちは、あべです。
私は15年以上の介護業界の経験をもとに、毎日の実践や気づきをシェアしています。
2023年10月2日は、X(旧Twitter)で次のポストをしました。
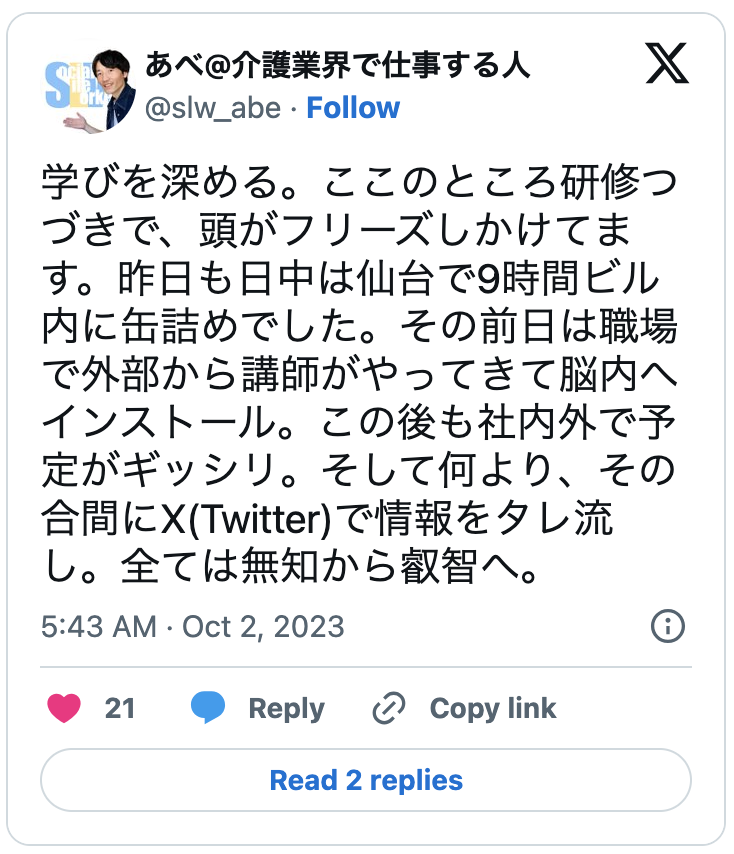
※画像をクリックすると、X(旧Twitter)が開きます。
このポストでは、「学びを深める」というテーマについて考えました。
介護の現場で働いていると、研修や講義を通して“知識”を得る機会が多くあります。ですが、それを自分の中で“叡智”にまで昇華できるかは、また別の話です。今回は、そんな「学びを深める力」について掘り下げていきます。
ポスト全文
学びを深める。ここのところ研修つづきで、頭がフリーズしかけてます。昨日も日中は仙台で9時間ビル内に缶詰めでした。その前日は職場で外部から講師がやってきて脳内へインストール。この後も社内外で予定がギッシリ。そして何より、その合間にX(Twitter)で情報をタレ流し。全ては無知から叡智へ。
セルフ解説
なぜこのポストを書いたのか
このポストを書いた当時、私は数週間にわたり研修続きのスケジュールを送っていました。外部講師を招いての研修、資格取得のための講義、そして自分自身が教える立場としての準備。それらが重なり、まさに「頭がフリーズしかけていた」状態でした。
ただ、疲労の中でも感じたのは、「学びの本質」でした。
例えば「自己研鑽」や「自己覚知」という言葉があるように、学ぶことは、単なる情報収集ではなく、“自分を磨くこと”であり、“無知を自覚する機会”でもあります。
人は知れば知るほど、自分の知らなさを知るようになる。そこからが「本当の学びのスタートライン」だと感じました。
このポストには、そんな気づきをポストに込めました。
学びを“知識”で終わらせないために
学びはインプットだけではなく、アウトプットすることで、はじめて理解が深まります。
現代は、学びや情報を得る手段が圧倒的に増えました。SNS、YouTube、オンライン講座。本を読まずとも“知識”が手に入る時代です。
ですが、それだけに「知った気」になってしまう落とし穴もあります。
学びを「深める」とは、頭の中に入れることではなく、“自分の経験と結びつけること”です。
例えば、研修で学んだ「傾聴の技術」を、翌日の利用者対応で意識的に実践してみる。
そうすることで、単なる知識が体験を通して“カラダ”に染み込み、自分の“叡智”へと変わっていきます。
“無知から叡智へ”とはどういうことか
この言葉には、私なりの意味を込めました。
「無知」は恥ではなく、“出発点”です。
人は、わからないことをわからないままにしておくと、成長が止まります。ですが、「自分にはまだ知らないことがある」と気づける人は、常に前進できる人です。
例えば介護現場でも、
- なぜこの方は同じ質問を何度も繰り返すのか
- なぜある利用者の方は急に怒るのか
といった場面に出会うたびに、興味や関心を持ち、「もっと深く知りたい」と思えるかどうかで、その後の対応力が変わります。
学びは、知識を“増やす”ことではなく、知識を“つなげる”ことです。
無知を認め、そこから叡智へ向かう。
それが、学びを“深める”ということです。
学び続ける人が信頼を得やすい理由
学び続ける介護職には、信頼される理由があります。
介護職は、「人を支える仕事」です。つまり、自分自身の“人間力”が、そのまま支援の質に反映されます。だからこそ、学び続ける姿勢が欠かせません。
知識だけでなく、「なぜそうするのか」「どうすれば本人にとってより良いのか」を考え続ける人は、現場で信頼を得やすくなります。
例えば、研修で得た“転倒予防”の知識をもとに、「床の滑りやすさ」「靴のサイズ」「歩行速度」などを自分の目で確かめ、改善提案をする。それが“知識を活かす”ということです。
介護は日常の延長線上にあります。利用者も、家族も、職員も、みな人としての関わりの中で支え合っています。だからこそ、学びは「人間理解」を深める手段でもあります。
学びの連鎖はチームを育てる
学びを深める人は、周囲にも良い影響を与えます。
例えば、「先日の研修でこういうことを聞いたんですが…」と一言シェアするだけで、会話が生まれ、チームの学びが連鎖していきます。
特にリーダーや教育担当者の立場であれば、学んだ内容を「どう伝えるか」も重要です。
難しい専門用語をそのまま話すのではなく、現場の事例に置き換えて説明する。それによって、チーム全体が同じ方向を向けるようになります。
介護現場における学びとは、“チームの知恵を高めること”。その積み重ねが、結果として「選ばれる施設」をつくる力になります。
今日から新たな一歩を
この記事をここまで読んでくださったあなたは、きっと何かしら共感や気づきを得てくださったと思います。大切なのは、その気づきを「行動」に変えていくことです。行動が変われば、日常の景色も少しずつ変わっていきます。
ここでは、今すぐ実践できるヒントをご紹介します。
例えば、
・学んだ内容を誰かに話す
→アウトプットすることで、記憶が定着し、自分の言葉として理解が深まります。
・1日1つ「気づきメモ」を残す
→小さな振り返りを習慣にすることで、学びが日々の中で積み上がっていきます。
・“なぜ”を3回以上繰り返す
→表面的な理解に終わらず、本質的な意味を見つけるための思考法です。
どの方法を選ぶか、どのように活かすかはあなた次第です。無理のない範囲で「今の自分にできること」から取り入れてみてください。その行動が、より豊かな日常生活へ向かう、改善に必要な大切な“第一歩”になります。
おわりに
この記事では、私自身が過去にX(旧Twitter)でポストした内容を改めて深掘りしました。
当時は伝えきれなかった「価値観」や「ものの見方」を通じて、少しでも新たな気づきやヒントになれば嬉しいです。
この記事のまとめ
- 学びを深めるとは、知識を“経験”とつなげること
- 「無知」を認めることが、叡智への第一歩
- 介護現場では、学びの共有がチームを強くする
- 学び続ける人が、信頼される人になる
現在は『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にポストしています。
最新の気づきや学びをリアルタイムで発信中です。ぜひお気軽に遊びに来てください!(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
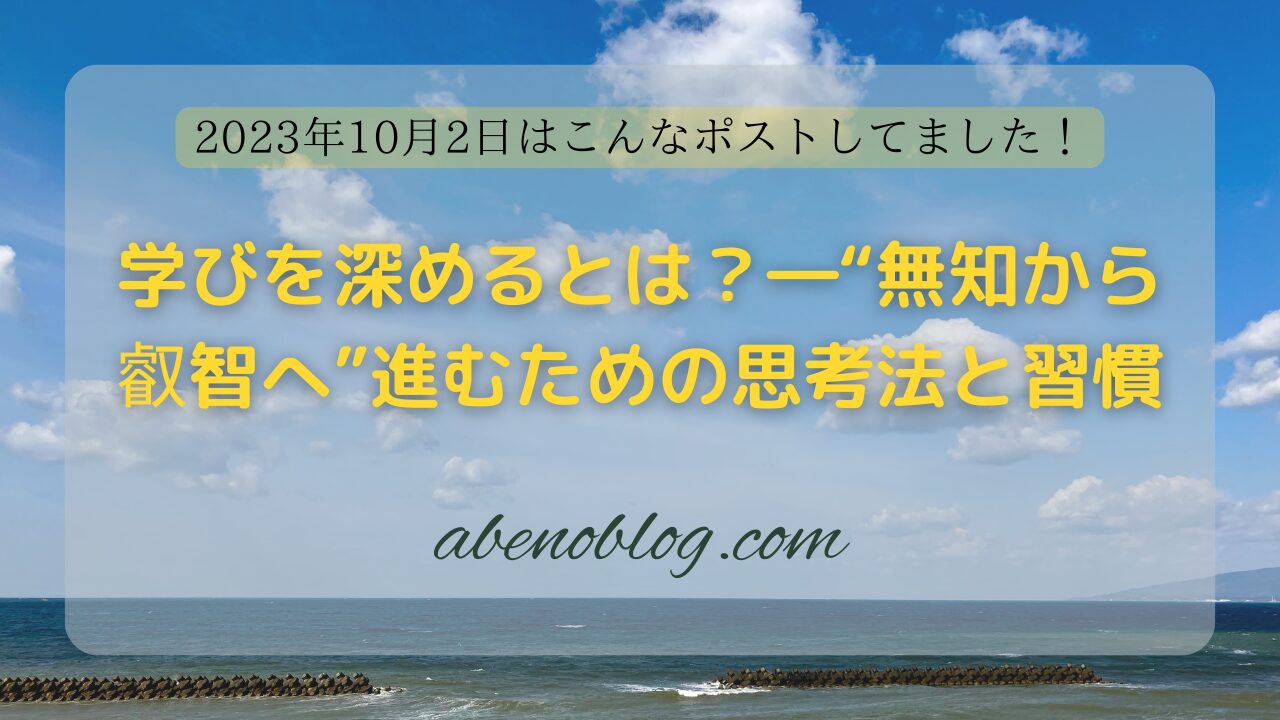
コメント