こんにちは、あべです。
私は15年以上の介護業界の経験をもとに、毎日の実践や気づきをシェアしています。
2023年8月8日は、X(旧Twitter)で次のポストをしました。
※うまく表示されない場合は、以下の「ポスト全文」でご確認ください。
この記事では、日本が直面する超高齢社会と2025年問題、そして国が掲げる健康寿命延伸プランについて深掘りします。
2025年になった今、現状や課題、そして健康寿命を延ばす方法についてお伝えします。
ポスト全文
コレ知ってました?今日本では超高齢社会の真っ只中で、2025年問題など差し迫った問題があります。それらを改善すべく、国は1つの大きな目標を掲げています。それが『健康寿命延伸プラン』です。この目標は2040年までに健康寿命を“75歳以上“にするというものです。ぜひ国民全員で目指したいですよね!
セルフ解説
なぜこのポストを書いたのか
2023年当時、介護現場で働く中で「2025年問題」が現実味を帯びてきていました。
利用者数の増加、人手不足、介護保険財源の圧迫など、現場の課題は山積みです。
そんな中で国が打ち出したのが「健康寿命延伸プラン」です。
これは「介護や医療に依存せず、自立した生活をできる期間を延ばす」ための国家プロジェクト。
介護の現場で日々向き合う私にとって、この方針は大きな可能性を感じました。
健康寿命延伸プランとは
健康寿命の定義と重要性
健康寿命は、「心身ともに自立し、介護を必要としないで生活できる期間」を指します。
平均寿命との差が短いほど、健康で過ごす期間が長いということです。
令和4年時点では、
- 男性:平均寿命81.05歳 / 健康寿命72.57歳(差8.49年)
- 女性:平均寿命87.09歳 / 健康寿命75.45歳(差11.63年)
(引用元:健康寿命の令和4年値について – 厚生労働省)
この差を縮めることが、介護費用の削減や生活の質(QOL)向上につながります。
なぜ「75歳以上」が目標なのか
2040年までに健康寿命を75歳以上に引き上げることで、
- 後期高齢者になる時期を遅らせる
- 介護・医療の負担を軽減する
- 高齢期も自立して暮らせる社会を実現する
ことが期待されています。
2025年問題との関係
2025年問題とは、団塊の世代(1947〜49年生まれ)が全員75歳以上になることで、高齢者人口が急増する現象です。
この影響で、医療・介護の需要と費用が急増します。
健康寿命を延ばすことは、この社会的負担を和らげる唯一の解決策の一つです。
介護現場で見える健康寿命の差
介護の仕事をしていると、同じ80代でも、元気な方と介護が必要な方に、次のような差があるように思います。
元気な方の多くは、
- 適度な運動習慣
- 栄養バランスの取れた食事
- 人との交流
- 前向きな心の持ち方
などを、長年意識し続けている印象です。
一方、健康寿命が短い方は、一概には言われませんが、生活習慣病や運動不足、孤立などが重なっているケースが多い印象です。
現場から見た介護予防の取り組み
私の勤務先である半日型デイサービスでは、
- 運動機能の向上訓練
- 関節可動域を保つストレッチ
- 口腔訓練や指導
- 趣味活動や会話の場の提供
といった介護予防を中心としたプログラムを行っています。
来所される方々の元気な姿を見ると、週1回でも外出して人と話すことは、認知症予防や抑うつ予防にも貢献していると感じてます。
健康寿命を延ばすために今日からできること
この記事が、あなたの行動を変えるきっかけになれば嬉しいです。今すぐ試せることを考えてみました。
• 1日10分の運動
→ウォーキングやラジオ体操でも効果があります。継続が鍵です。
• 人と話す習慣
→会話は脳を活性化し、孤立防止にもなります。
• 「プラス1健康食材」を足す
→魚、納豆、野菜、発酵食品などを日々の食事に。
• 食事前のパタカラ体操
→口を大きく動かし、唾液の分泌を良くします。
• 趣味や学びを継続
→好奇心は心身の若さを保ちます。
どの方法を選ぶか、どのように活かすかはあなた次第です。無理なくできることから今すぐ試してみてください。
おわりに
この記事では、2023年にポストした内容を2025年の視点で深掘りしました。
健康寿命を延ばすことは、私たち一人ひとりの生活の質を守るだけでなく、社会全体を守る行動です。
この記事のまとめ
- 健康寿命は「自立して暮らせる期間」
- 2025年問題は医療・介護負担を急増させる
- 健康寿命75歳以上を目指すには、運動・食事・交流が不可欠
- 介護予防は現場でも家庭でも取り組める
現在は『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にポストしています。最新の気づきや学びをリアルタイムで発信中です。ぜひお気軽に遊びに来てください!(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
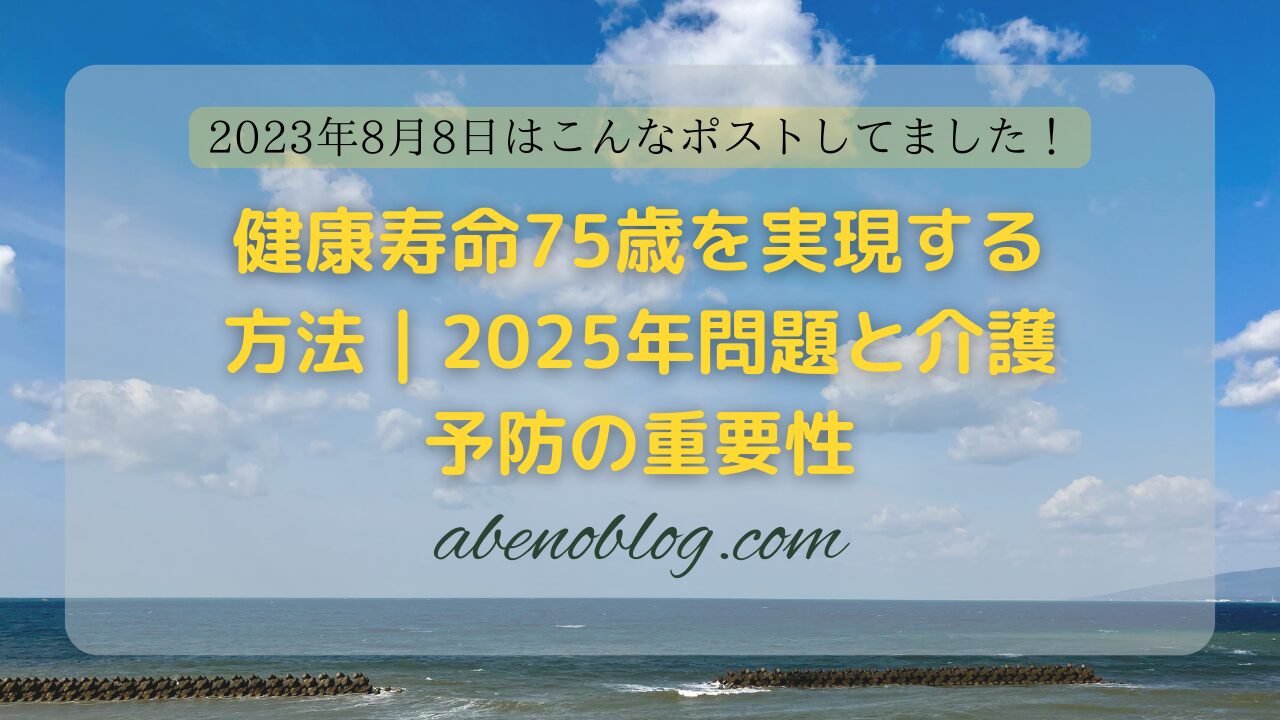
コメント