こんにちは、あべです。
2023年4月13日の私は、X(旧Twitter)に次のポストをしていました。
ポストの全文
【ソーシャル・ライフワーカー】とは、私が考えた「造語」です。
一般的な【ソーシャルワーカー】という言葉は、【名称独占】である【社会福祉士】を指しますので、私はその中にある「ソーシャル」という言葉と、「生きがいを感じている人」を指す【ライフワーカー】という言葉を合わせました。m(_ _)m
セルフ解説
この記事では、1ポストでは伝えきれなかった、「ソーシャル・ライフワーカー」という言葉に込めた私の思いを深掘りします。
「ソーシャル・ライフワーカー」という考え方
はじめに、「ソーシャルワーカー」という言葉は、国家資格である「社会福祉士」を指すことが一般的です。
私は、この資格をお持ちになられて、医療機関や福祉施設などでご活躍されている方々を尊敬し、憧れの思いがあります。そして、この資格は“いつか取得したい資格”の一つです。、
ですが、それとは別に、私はこの“福祉”を超えて、もっと広い範囲で“ソーシャル”という単語と“ワーカー”という単語を活用しようと思いました。
そこで考えたのが、「ソーシャル・ライフワーカー」という言葉です。
この言葉の意味は、社会と関わりながら生きがいを持って活動する人と定義します。
例えば、次のような人たちが当てはまります。
• 介護・福祉の現場で働く人(私自身もこの業界に長く携わっています)
• 家族を支える主婦・主夫(家庭という社会を支える重要な役割)
• 地域活動やボランティアに関わる人
• 会社や組織の中で、誰かの役に立とうと努力する人
• SNSやブログを通じて、人の役に立つ情報を発信する人
つまり、「ソーシャル・ライフワーカー」とは、特定の資格や職業に縛られず、「生きがいを持って社会に関わるすべての人」を指す考え方です。
なぜ「ソーシャル・ライフワーカー」を提唱するのか?
正直なところ、私は今の社会を見ていて、「やりがい」や「生きがい」を持って活動している大人は少数派ではないかと感じています。
また、現代人の中には、ただなんとなく日常を過ごし、何か不都合があると、他人のせいにしたり、環境のせいにしたりと、他力本願の人も、世の中には一定数いるのが現実です。
もちろん、人にはそれぞれの価値観があります。
ですが、本来ならば社会の見本となり、次世代に希望を示すべき大人たちがこのような状態でいることには、私は強い危機感を抱いています。
では、どうすればよいのでしょうか?
私は、まずは自分自身が「依存」から抜け出し、「自立・自律」することが大切だと考えています。
「誰かが何とかしてくれるだろう」という考えを捨て、自分の人生に責任を持ち、生きがいを持って社会に関わること。それが、次世代に良い影響を与え、社会全体をより良くする第一歩になると信じています。
「依存」から「自立・自律」へ──社会全体の変化へつなげるために
「自立・自律」とは、決して「誰の助けも借りずに生きる」ということではありません。
むしろ、自分の意思を持ち、自分で決めて行動できるようになることが重要です。
そうすれば、必要なときに適切な形で助けを求めることができ、より健全な助け合いの社会が生まれます。
例えば、
• 「自分のやりたいこと」を持って行動する人は、周囲に良い影響を与える
• 「自分で考え、決断する力」を持つ人が増えれば、社会全体の活力が増す
• 「他人のせいにしない人」が増えれば、責任感のある文化が育つ
こうした変化が積み重なれば、社会はもっと良くなっていくはずです。
「ソーシャル・ライフワーカー」の広がりを願って
この言葉は、まだ一般的なものではありません。
ですが、私はこの考え方が広まることで、「生きがいを持って社会と関わる人」が増えていくことを願っています。
資格や職業に関係なく、誰もが誰かの役に立てる。
そして、それが「自分の生きがい」につながる。
そんな社会が実現できたら、もっと温かく、活気のある世界になるはずです。
まずは、自分自身が「ソーシャル・ライフワーカー」として生きる。
その姿勢が、社会全体を変える一歩になると信じています。
皆さんは、この考え方についてどのように思いましたか?
ぜひ、ご意見をお聞かせください!
おわりに
このシリーズ投稿は、リアルな生活に負担のない範囲で不定期に更新します。
現在は、X(旧Twitter)で『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にポストしています。
良かったら、最新のポストに遊びに来てください。(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
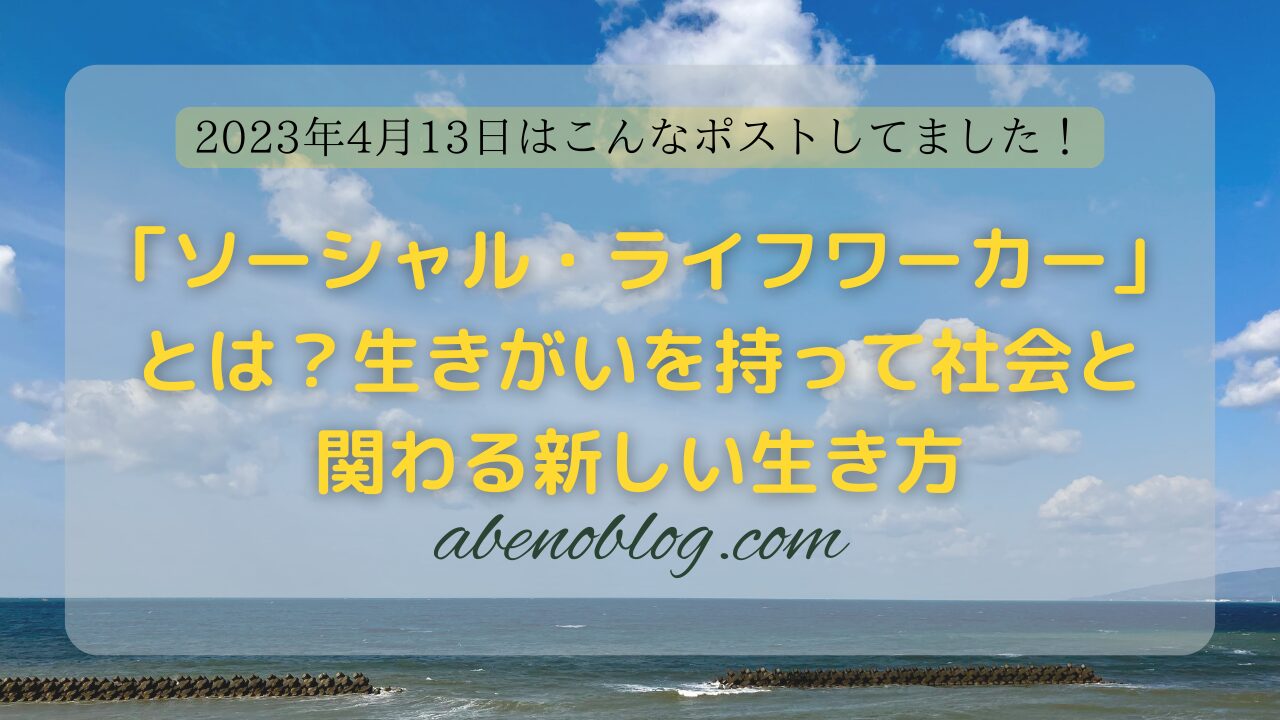
コメント