こんにちは、あべです。
私は15年以上の介護業界の経験をもとに、毎日の実践や気づきをシェアしています。
2023年8月5日は、X(旧Twitter)で次のポストをしました。
※うまく表示されない場合があります。その場合は、以下の「ポスト全文」でご確認ください。
このポストでは、「問題発生時の焦りを抑え、冷静に正しい行動を選ぶための考え方」について考えました。
緊急事態になると、つい焦って動き出してしまうものです。ですが、その前に「立ち止まる時間」を持つことが、結果的に解決を早めることがあります。
ポスト全文
何か問題が起きた時は、なんとかならないか“手段や方法“を探しますよね?でも、それが緊急であればあるほど気持ちが焦って空回りしてしまいます。そのような時こそ一端立ち止まり、「何をすべきか」の前に「どうあるべきか」と問いかけてみて下さい。すると割と早く正しい“手段や方法“が見つかります。
セルフ解説
なぜこのポストを書いたのか
このポストを書いた背景には、私自身の介護現場での経験があります。
介護の現場では、利用者さんの体調変化や事故、急な対応が求められる場面が多々あります。特に新人の頃は、何か起きるたびに「どうしよう!」と慌ててしまい、結果として判断が遅れたり、間違った方向に進んでしまったこともありました。
その経験を通じて気づいたのは、「行動する前に、自分のあり方を確認すること」の重要性です。
焦って動くと、見落としや誤判断が増えます。反対に、一度立ち止まって「自分は今どうあるべきか」を考えることで、冷静さを取り戻し、正しい手段が見えやすくなります。
「どうあるべきか」を優先する理由
1. 焦りは判断力を奪う
心理学的にも、緊急時のストレスは視野を狭め、認知バイアスを強めると言われています。これは「トンネル・ビジョン」と呼ばれ、目の前の一つの選択肢に固執してしまう状態です。
「どうあるべきか」を先に考えることで、この視野の狭まりを防ぐことができます。
2. 「あり方」は判断の基準になる
例えば介護現場なら、どんなに急な事態でも「利用者さんの尊厳を守る」という軸があれば、選択肢を絞りやすくなります。これはビジネスや家庭でも同じです。自分の中に「優先すべき価値」があれば、迷いが減り、決断が早くなります。
3. 長期的に信頼を築ける
短期的な成果だけを求めて動くと、その場は乗り切れても信頼を失うことがあります。ですが「どうあるべきか」を軸に動くと、結果的に人間関係も信頼も守れます。
実生活や介護現場との関連性
介護の現場では、例えば利用者さんが急に転倒したとき、「すぐに起こそう」と思うのは自然な反応です。ですが、焦って抱き起こすと二次的なケガを招く恐れがあります。
ここで「どうあるべきか」を考えれば、「まず安全確保」「呼吸・意識の確認」「必要なら救急要請」という冷静なステップが踏めます。
家庭でも同じです。子どもが泣き出したとき、「早く泣き止ませなきゃ」と焦るより、「今この子は何を感じているのか」を先に考えることで、より適切な対応ができます。
つまり、緊急時こそ「手段」より「あり方」を先に確認することで、結果的に最短で正しい行動にたどり着けます。
行動のヒント
この記事が、あなたの行動を変えるきっかけになれば嬉しいです。今すぐ試せることを考えてみました。
・何かを始めるときの第一歩
→ 行動する前に「自分のあり方」を1つ書き出す。これは判断の軸になります。
・自分を変える小さな行動
→ 日常の小さな困りごとでも、すぐ動く前に5秒だけ立ち止まって考える習慣をつける。
・視点や考え方の切り替え方
→ 「何をするべきか?」ではなく「どうありたいか?」と問い直す。すると選択肢が変わります。
どの方法を選ぶか、どのように活かすかはあなた次第です。無理なくできることから今すぐ試してみてください。
おわりに
この記事では、私自身が過去にX(旧Twitter)でポストした内容を改めて深掘りしました。
当時は伝えきれなかった「価値観」や「ものの見方」を通じて、少しでも新たな気づきやヒントになれば嬉しいです。
この記事のまとめ
• 緊急時こそ焦りが判断を誤らせる
• 「何をするか」より先に「どうあるべきか」を考える
• 介護現場や家庭でも、この考え方は有効
現在は『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にポストしています。
最新の気づきや学びをリアルタイムで発信中です。ぜひお気軽に遊びに来てください!(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
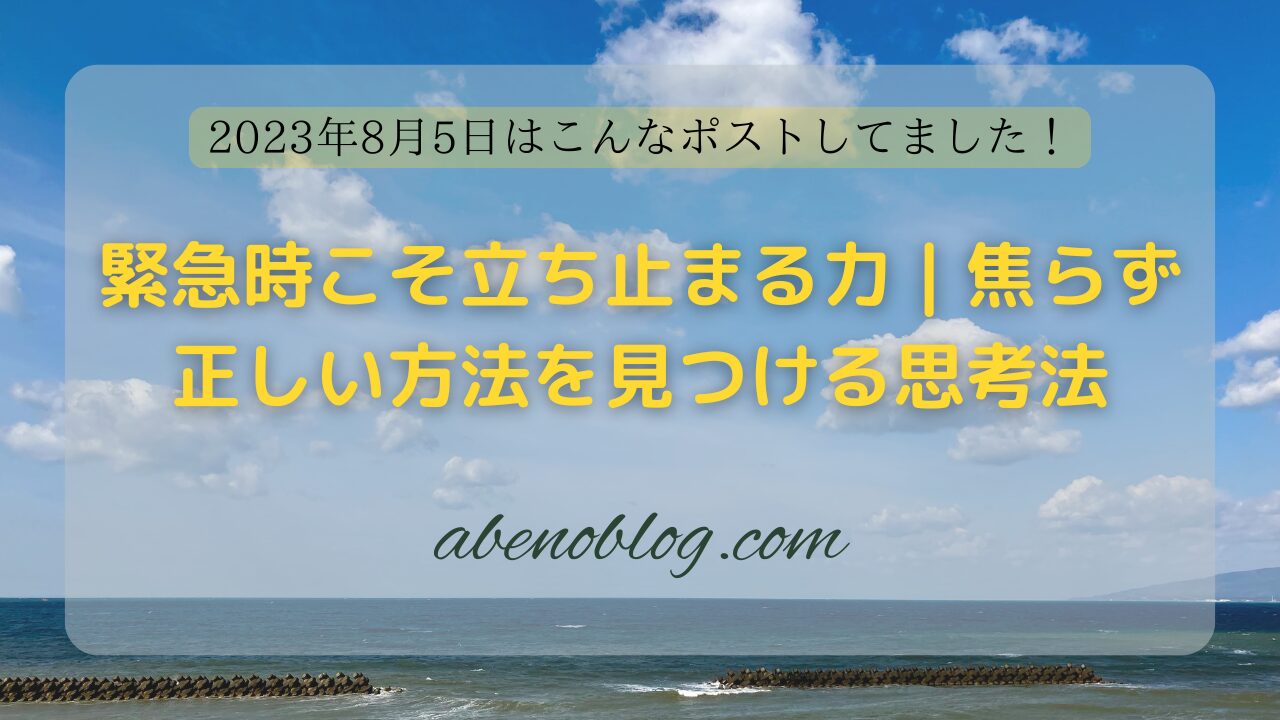
コメント