こんにちは、あべです。
私は15年以上の介護業界の経験をもとに、毎日の実践や気づきをシェアしています。
2023年8月4日は、X(旧Twitter)で次のポストをしました。
※うまく表示されない場合があります。その場合は、以下の「ポスト全文」でご確認ください。
このポストでは、「行き詰まった時にどう相談すれば解決が早くなるか」というテーマについて考えました。
誰しも、仕事や日常でわからないことにぶつかり、頭の中が混乱してしまう経験はあるはずです。そんな時、ただ相談するだけでなく、伝え方を工夫することで一気に道が開ける場合があります。
ポスト全文
【解決に導く相談の仕方】「わからない事」を独りで考え込んで、行き詰まることはないですか?そういう時は、誰か聞き手の方を見つけてお伝えしてみましょう。ポイントは、“わかる範囲“と“わからない範囲“を整理しながらお伝えすることです。これだけで、かなりの確率で“解決の糸口“が見つかります!
セルフ解説
なぜこのポストを書いたのか
このポストは、私自身が介護現場や日常生活で「悩みや疑問を抱えたまま行き詰まる人」を何度も見てきた経験から作成することにしました。
私も昔はそうでしたが、「どう相談すれば解決が早いか」を知らないと、せっかく相談しても相手を混乱させたり、結局モヤモヤが残ったままになったりします。
特に介護の現場では時間が限られており、相談するにも効率性が求められます。そこで、「わかること」と「わからないこと」を整理して伝える方法を多くの人に知ってほしいと思いました。
効果的な相談は“整理”から始まる
「相談力」という言葉がありますが、これは単に質問する力ではなく、「相手にとって答えやすい形で情報を渡す力」です。
例えばこんな違いがあります。
• 悪い例
「なんかうまくいかないんですよね…どうすればいいですか?」
→抽象的すぎて相手が状況を想像しづらい。
• 良い例
「利用者さんの入浴介助で時間が押してしまうことが多いです。私がやっている流れは〇〇→〇〇ですが、この部分で時間がかかっています。何か改善の方法はありますか?」
→事実と困っているポイントが明確なので、相手は的確なアドバイスがしやすい。
つまり、相談のコツは 「現状の把握」と「課題の明確化」 です。
これを意識すると、相談した相手の思考も整理され、答えが見つかる確率が格段に上がります。
実生活や介護現場との関連性
介護現場では、相談の質がチーム全体の動きに直結します。
例えば、ある職員が「昨日の利用者さんの様子、ちょっと違ったんですけど…」とだけ言うと、他の職員たちは何から確認すべきか迷います。
ですが、「昨日の利用者さんが、普段は声をかけるとすぐに返事があるのに、3回呼んでも反応が遅かったです。食事量は変わらないのですが、歩行時に少しふらつきが見られました」と言えば、体調や意識レベルの変化、転倒リスクなど、判断材料が揃います。
これは家庭でも同じです。
たとえば子どもが「お腹が痛い」と言った時に、「どのあたりが痛い?いつから?どんな痛み?」と聞き出せると、医療機関に伝える情報も正確になり、対応も早くなります。
行動のヒント
この記事が、あなたの行動を変えるきっかけになれば嬉しいです。今すぐ試せることを考えてみました。
• 相談前に「3つの整理」をする
1. 現状(わかっていること)
2. 問題点(困っていること)
3. 不明点(知りたいこと)
→この整理ができると、相手もすぐに状況を理解できます。
• 聞き手の負担を減らす
→相談相手が状況把握に時間を取られないよう、具体的な情報をまとめておく。
• 相談内容をメモしてから話す
→頭の中だけで考えると情報が抜けやすいですが、メモすれば整理しやすくなります。
どの方法を選ぶか、どのように活かすかはあなた次第です。無理なくできることから今すぐ試してみてください。
おわりに
この記事では、私自身が過去にX(旧Twitter)でポストした内容を改めて深掘りしました。
当時は伝えきれなかった「価値観」や「ものの見方」を通じて、少しでも新たな気づきやヒントになれば嬉しいです。
この記事のまとめ
• 効果的な相談は「わかること」と「わからないこと」の整理から始まる
• 情報を整理してから伝えると、解決の糸口が見つかりやすい
• 介護現場でも家庭でも、相談の質が対応スピードを左右する
現在は『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にポストしています。
最新の気づきや学びをリアルタイムで発信中です。ぜひお気軽に遊びに来てください!(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
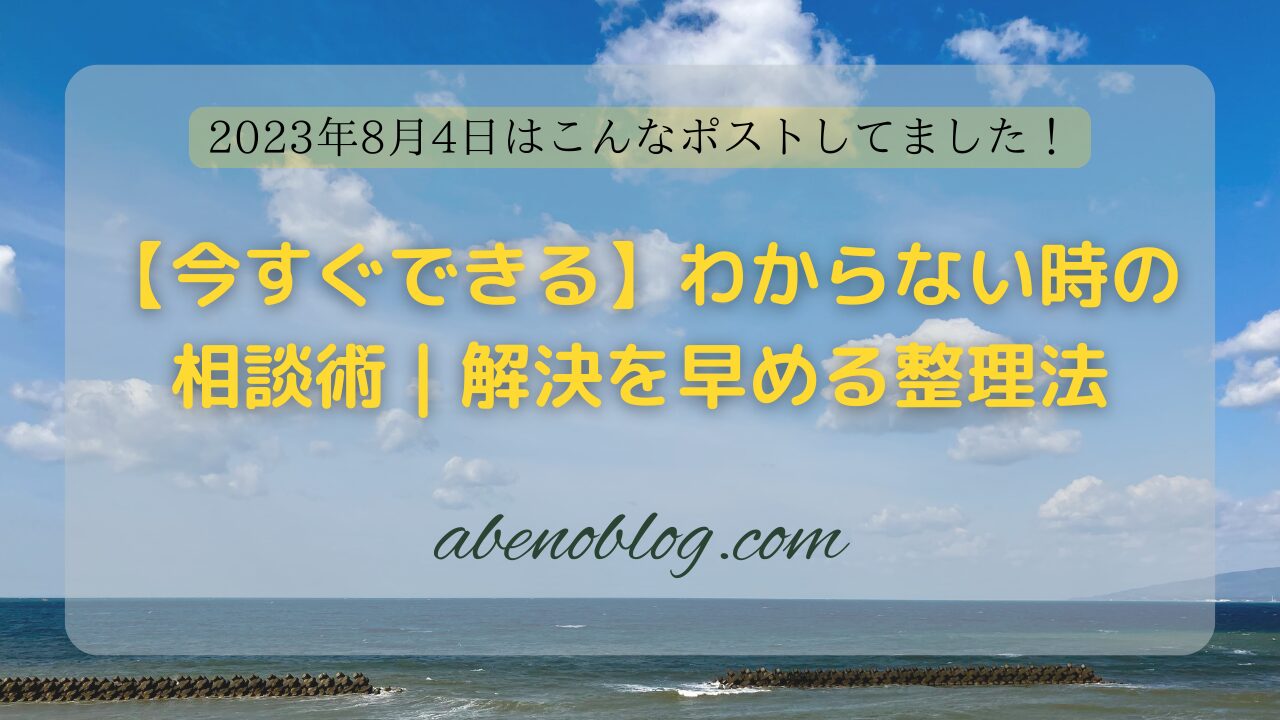
コメント