こんにちは、あべです。
私は15年以上の介護業界の経験をもとに、毎日の実践や気づきをシェアしています。
2023年10月4日は、X(旧Twitter)で次のポストをしました。
このポストでは、「集中力を妨げる中断の恐ろしさ」について考えました。
仕事や家事、介護などで「手を止める」瞬間は誰にでもあります。ですが、そのたびに思考はリセットされ、再び集中するには時間とエネルギーを要します。この記事では、中断がもたらす影響と、その対策について深掘りします。
ポスト全文
中断の恐ろしさ。何か作業をしていると、電話が鳴ったり話かけられて“手を止めること“って多いですよね。実はソレ、かなり非効率です。集中して何かを仕上げる、創造する時は特にです。人は中断から再び集中するまでに20分以上かかるとされます。なので環境はとても大事です…とわかってはいますが…。
セルフ解説
なぜこのポストを書いたのか
このポストした頃は、社内で重要な書類の作成や校正作業をしていました。集中して文書に目を通していると、電話が鳴り、返答し、続きから目を通す。すると今度は社員から相談を受け、返答し、また続きから目を通す…。気づけば時間だけが過ぎ、文章のリズムも思考の流れも崩れていました。
特に「創造的な作業」は、深い集中状態(いわゆる“フロー”)に入ることで質が上がります。ですが、一度中断されると、その集中を取り戻すのに想像以上の時間がかかります。私自身も“中断”の恐ろしさを体感した瞬間でした。
この体験から、「集中できる環境をつくること」も立派な仕事の一部だと再認識し、このポストを作成しました。
中断が「思考の断絶」を生む理由
私たちは「同じ作業に戻れば、すぐ再開できる」と思いがちですが、実際はそうではありません。心理学や脳科学の研究によると、人は中断から再び集中状態に戻るまで平均23分かかるとされています。
なぜそこまで時間がかかるのか。理由は「脳の切り替えコスト」にあります。
脳はひとつのタスクに集中しているとき、関連する情報をワーキングメモリに保持しています。しかし、電話や会話などで中断されると、その情報が一部消失してしまい、再び思考の流れを取り戻すために“再構築”が必要になるそうです。
この“再構築”にかかる時間が、いわゆる「中断の代償」です。
特に、文章を書く・企画を立てる・報告書を作るなど、「創造的な業務」ほどこの代償が大きくなります。単純作業ならすぐ戻れますが、考える仕事では“思考のリズム”が命。たった一度の中断が、生産性を大きく下げることがあります。
実生活や介護現場との関連性
介護の現場でも、「中断」は日常的に起こります。例えば、記録を書いている途中に呼び出される、介助中に別の相談を受ける、電話が鳴る…そんなことは日常茶飯事です。
一見すると仕方のないことですが、ここにこそ“工夫”の余地があります。
■ 中断を減らす工夫①:時間を区切る
介護現場では「対応」と「記録」を同時にこなすことが多いですが、時間をあえて“区切る”ことが有効です。
例えば、「午前の記録は○時から○時まで」と決め、その時間だけは他の対応を別職員がフォローする。これだけで記録の質もスピードも上がります。
■ 中断を減らす工夫②:共有ツールを活用する
中断の多くは「伝達ミスを防ぐため」の声かけや確認です。つまり、情報共有の仕組みが整っていれば、声かけの必要も減ります。
ホワイトボードやタブレットなどを活用して「今、誰が何をしているか」を見える化することで、声かけが減り、集中時間を守りやすくなります。
■ 中断を減らす工夫③:声かけルールを設ける
「話しかけていいタイミング」をチームで共有するのも効果的です。
例えば、「記録中は声をかけない」「対応中は目線で合図する」など。小さなルールですが、集中を守る文化が育ちます。
介護の現場はチームワークが大切です。介護職や看護師、機能訓練指導員など、それぞれの専門職がお互いの職種と役割を理解し、協力し合える職場環境を目指したいものですね。
今日から新たな一歩を
この記事をここまで読んでくださったあなたは、きっと何かしら共感や気づきを得てくださったと思います。大切なのは、その気づきを「行動」に変えていくことです。行動が変われば、日常の景色も少しずつ変わっていきます。
ここでは、今すぐ実践できるヒントをご紹介します。
・「集中時間」をスケジュールに入れる
予定表に「集中タイム」を組み込みましょう。たとえば午前の1時間だけでも「電話を取らない」「通知をオフにする」時間をつくるだけで、生産性がぐっと上がります。
・小さな“完了体験”を意識する
集中が切れたときは、「ここまでやった」と自分で区切りをつけると再開しやすくなります。タスクを細分化することで、中断しても再構築の負担を減らせます。
・環境の“音”を整える
静かな環境を作ることが難しい場合は、イヤホンや環境音アプリなどの活用もおすすめです。集中に適した音環境は、思考の深さを保つ助けになります。
どの方法を選ぶか、どのように活かすかはあなた次第です。無理のない範囲で「今の自分にできること」から取り入れてみてください。その行動が、より豊かな日常生活へ向かう、改善に必要な大切な“第一歩”になります。
おわりに
この記事では、私自身が過去にX(旧Twitter)でポストした内容を改めて深掘りしました。
当時は伝えきれなかった「価値観」や「ものの見方」を通じて、少しでも新たな気づきやヒントになれば嬉しいです。
この記事のまとめ
- 「中断」は思考の断絶を生み、再集中には20分以上かかる
- 集中できる環境づくりは“生産性の投資”である
- 介護現場でも「中断を減らすルール」や「時間の区切り」で効率が上がる
- 環境と意識を整えることで、仕事の質も自分の余裕も変わる
現在は『毎日1ポスト』を目標に、毎朝6時頃にポストしています。
最新の気づきや学びをリアルタイムで発信中です。ぜひお気軽に遊びに来てください!(@slw_abe)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
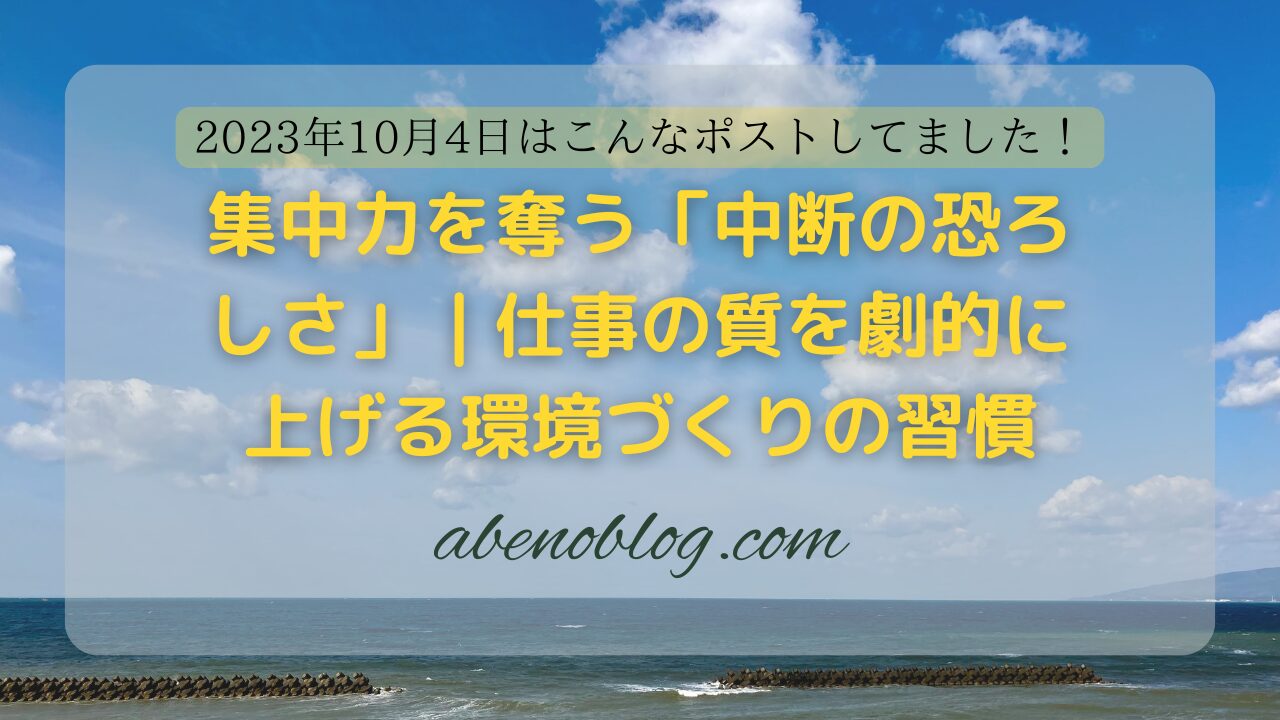
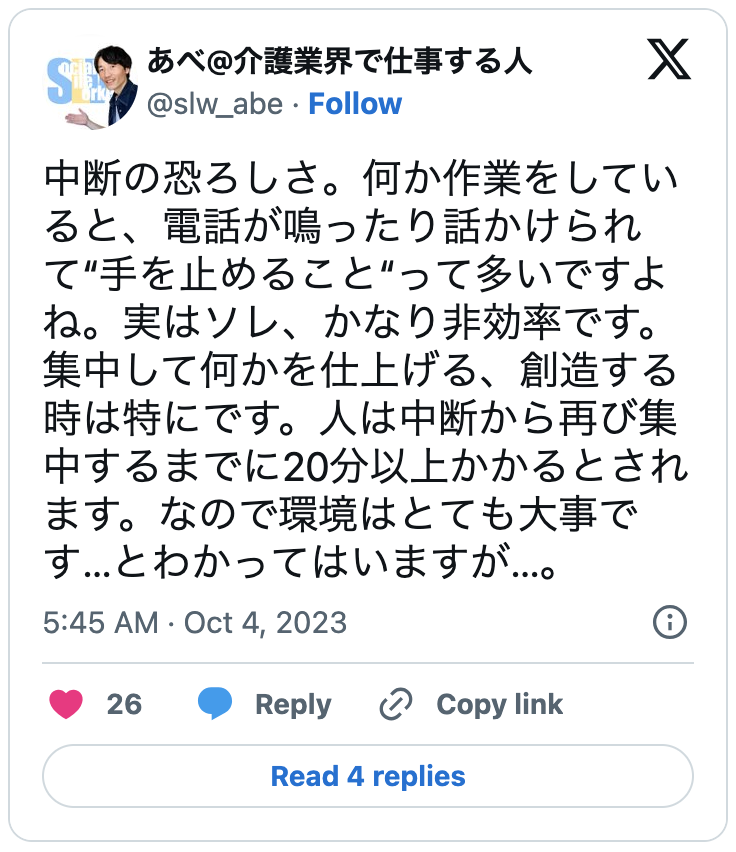
コメント